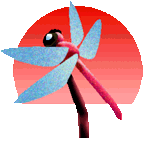
地名は歴史の蓄積が醸し出す独自の色彩を伴っている
地名は無形の文化財
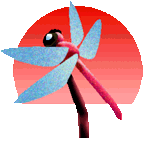 |
かくれた歴史の発見 和歌山市編 地名は歴史の蓄積が醸し出す独自の色彩を伴っている 地名は無形の文化財 |
南 畑(地形)
大河内の南西にあり、黒岩に通じる谷間で、その谷口に広野が開け、山東荘の南部にあることにより南畑に名がある
向
地名向は川向、橋向の義か、もと俗に橋ノ向といった
元寺町
江戸期、お寺が多く集められお城の北入口を防備していたが、1633年(寛永10年)大水害の 整備で吹上げの南へ移転したので元寺町となる
元博労町(町人町)
城北の堀川に面し馬の売買・周旋に従事した者の居住地
元町奉行丁(江戸期 武家地)
江戸期、広瀬に東・西番所が月番制で与力3人、同心25人、書役3人が町政全般を指揮する 町奉行所が設置されていた事に由来する
本 脇(地形)
もと加太の出村で、往昔この辺は紀の川の海口であったこと すなわち本脇の名はもと川傍、 川脇の義であろう すでに正和3年(1314)の文書に見えている この地は往時亀川川村への 渡船場であった
森小手穂(歴史)
もとは森村と小手穂の二村であった 森は地内に森林があった また小手穂はおてぼりと訓し地内に弘法大師御手掘といい伝えて早魃のときも涸れず、降雨の時にも濁らずこんこんと湧き出る有名な井泉があった為それぞれに村名としたが、明治初年に合併して一村となった
薬種畑
紀州藩の薬草園があった所
薬勝寺(寺)
もと多田ノ井の内で、往昔この地は薬小寺、薬王寺という真言宗の二大寺院の境内であった が天正の兵乱で伽藍衰廃した為、附近大和佐村の人家が寺の廃跡に移り寺名を取って村名 とした
安 原
地名安原はもと江南、松原、相坂、馬場、井戸を統べる村名、荘名であったが、後世榎原、夙 両村を加え、新出島村を開いて、計8箇村を安原荘とし、明治22年町村実施に際して夙、榎 原を除く旧安原六箇所村に、旧五箇の荘の吉原、広島、冬野、朝日、旧多田郷の内仁井辺、 小瀬田、薬勝寺、本渡家各村を加え計14箇村をもって新制による
山口西(地理)
山口の名は雄の山の義で応安(1368)の文書に山口の荘が初めてみえている
湯屋谷(地形)
中世山口村と称したが藩初湯屋谷村と改めた 附近葛城山系の滝畑、山中渓谷などに鉱泉湧 出あり、ここにも昔時鉱泉が沸いた為であろうか、または駅場として風呂屋の設備があった為 であろう
吉 里
もと安原の荘の内で夙村といった 夙は宿で、昔時生産の者が村界寺に仮屋を建て、産穢終わ るまで止宿する習慣があったが、ここはその産所の地であった 明治12年10月良里と改称し 同22年4月西山東村に編入された
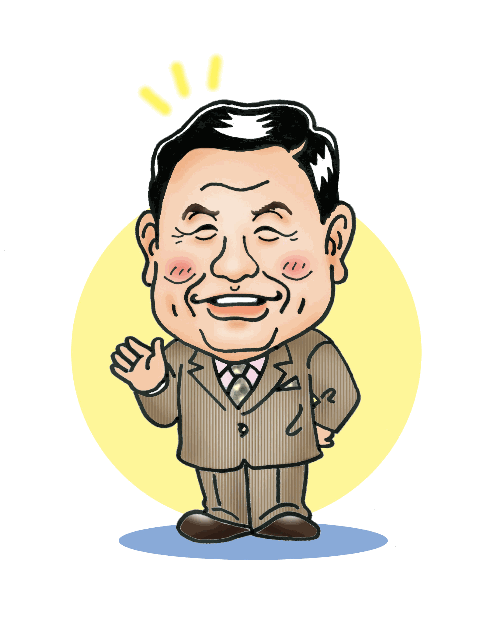 |
参考資料 角川地名大辞典 和歌山市史 和歌山県史人物編 紀州の伝説(角川書店) 紀州の民話 続風土記 |